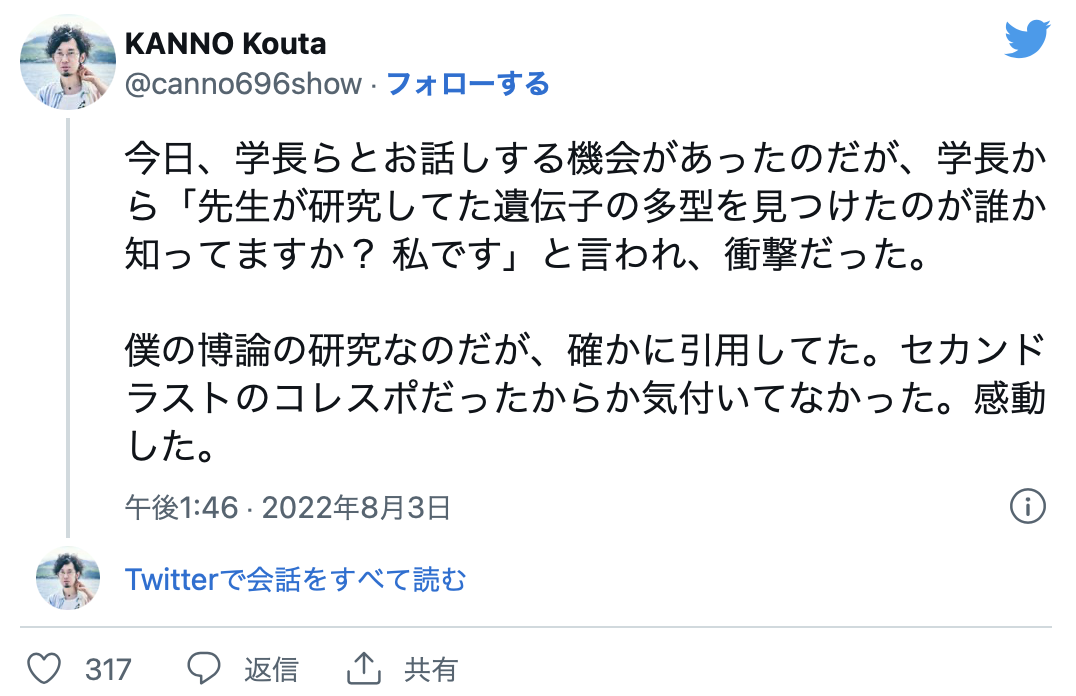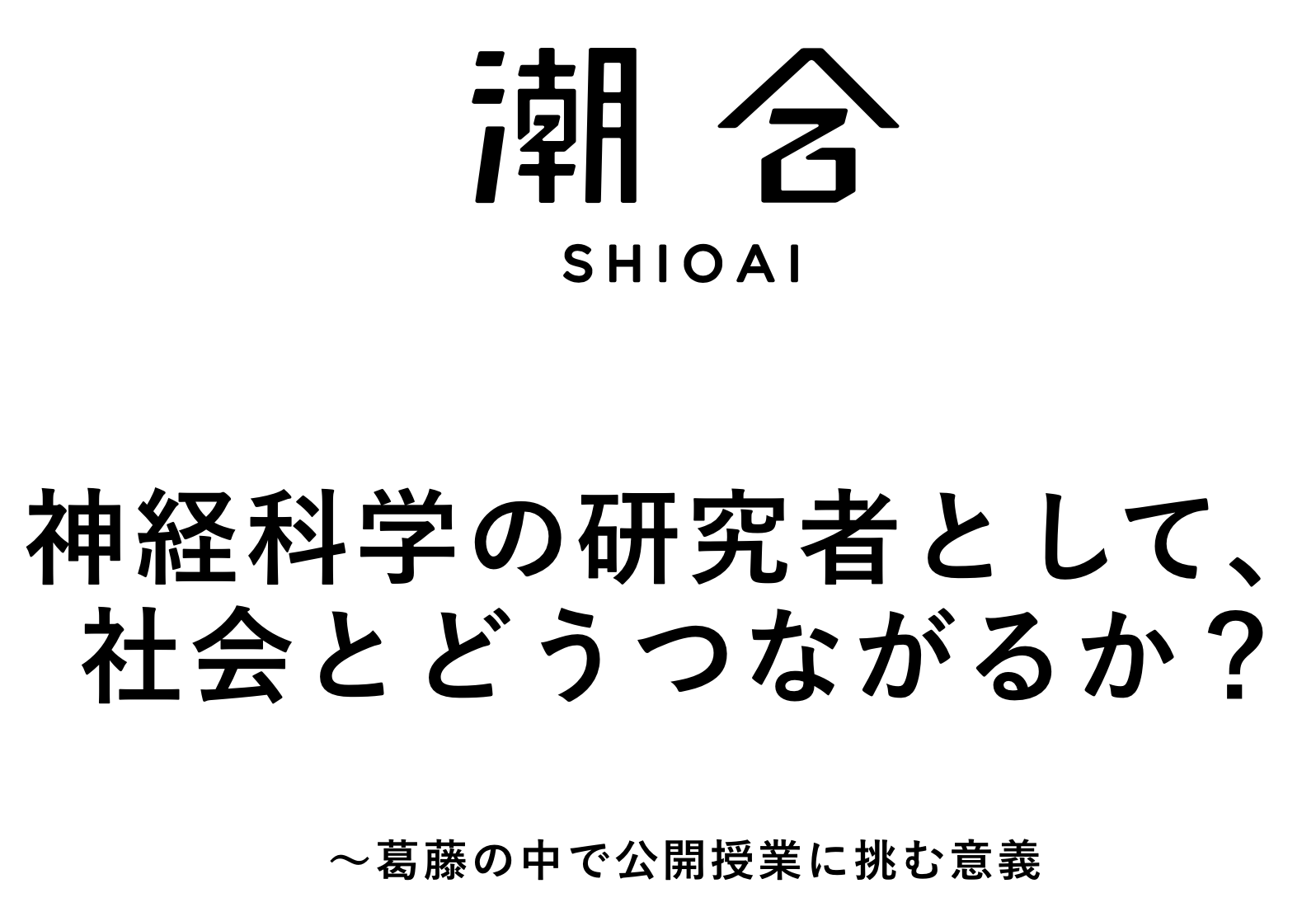学びのパターン・カタチ・リズム
先日、3710 Lab のサイトに第3回全国海洋サミットというイベントのレポートを書いた。
3710 Lab とは、高校バスケ部同級以来の友人である田口康大が、東大の海洋教育促進センターで働き始めたことをきっかけに、SYNAPSEの活動をしていた私に「何か既存の大学や教育といった枠組み以外の試みを一緒にできないか?」との誘いを受け、始まったものだ(公式の活動理念はこちら)。
田口は、さまざまな小中学校や高校に出向き、現場の先生と共同で授業内容をつくることを通して、海洋教育を促進している、というわけだ。今日(2016年3月21日)は、その中でも東大教育学部付属の中高一貫校で行われた授業の、この一年の集大成が、シンポジウムという場で披露された日だった。
第3回東京大学海洋教育フォーラム 「海と人との関わりを探る―ディープ・アクティブラーニングの方へ」
http://rcme.oa.u-tokyo.ac.jp/events/post886.html
その授業とは、海洋サミットのレポート後編でも触れた、ドキュメンタリー映画製作を手法として用いた地域社会研究、課題別学習「海(Sea)」である。生徒たちが沖縄についての事前学習を行い、その後、現地に赴き、それぞれの関心に基づいたテーマに関する質問を、実際に沖縄の人々にインタビューする。そのため、事前学習でもビデオカメラを用いたインタビューの練習も行なっているのだが、事前学習、インタビューの練習、実際のインタビュー、ビデオの編集という、生徒たちのドキュメンタリー制作場面自体をドキュメンタリーした映画の上映も行われた。
かなり、メタな視点で行われた授業と言える。
この授業、もしくは東大としての田口の試み、とても面白いものだと思うのだが、それが、授業の関係者以外に知られないのは、とてももったえない。こういう活動をしていること自体が、コンテンツになる。そこで、3710 Labを始めたとも言える。
同時に、これはSYNAPSEにとっても、創設の理念であった。SYNAPSEの前身的活動として、東大大学院時代に頂いた学生企画コンテストの賞があるのだが、そこでも我々は「大学が行なっている活動は、少し編集の手法を加えるだけで、十分人々の関心を引くことができるコンテンツになる」という旨を主張していた。それを、大学を「開く」ことで、社会に伝えていけるのだと(当時は、事業仕分けの直後だったという背景を思い起こして聞いて欲しい)。
さて、そのドキュメンタリ制作をドキュメンタリした映画『課題別学習』であるが、内容に関しては、3710 Lab としても後日レポートをするので、詳細はそちらに譲ることとして、私のざっくりとした感想と、学びとは何か、もしくは、高校生だった頃の自分、などについて、思い返してみたい。また、その監督・福原悠介も、私と田口の高校の同級生であること、ここで明かしておきたい。
何より驚いたのは、そこに写っていた中高生(中高一貫校の3-4年生の混合クラスであった)の表情が、いわゆる、良い顔をしていたことだ。シンポジウム後には茶話会があったので、そこで実際に生の生徒たちにも会ったし、前回取材をした私のことを覚えていてくれた生徒もいたので、その表情は私もよく覚えていたのだが、映画の中にいた生徒たちは、子供というには、その真剣な表情が、あまりにも大人だったのだ。しかし、実際に会った生徒たちは、それよりも、ずっと無邪気な「中高生」に見えた。
沖縄での本番のインタビューを前に、生徒たちが学んだことは何か。カメラを前にして、自分の意見を聞かれる、ある種、普段表現しない自分の考え、中身、内面を表現することを要求されること。また、それが切り取られること。他人によって解釈されてしまうこと。生徒たちは、おそらく、それを知った。逆に、自分たちはこれから、その切り取る行為を、沖縄の人たちにするのだということを。これは、考え方によっては、暴力的な行為である。また、このようにカメラというものを通して人の目、人に見られるということ、を意識することで「自分」を「演じる」ということを体感したであろうと思う。
一人の生徒がドキュメンタリ制作を通して、言葉を選ぶことの責任を意識するようになったとの旨を述べた。これは、私なりの解釈では、上記のような暴力性を知った、ということだと思う。
ドキュメンタリという「舞台」を用意されたことで生徒たちは、なりたい自分、求められる自分、人から印象を持たれる自分、様々な姿を意識し、どのような自分であるべきかに迷いながらも着地点を探し、自分を「演じた」と言えるのだと思う。それは、私の感じた「大人」っぽさだったのではないか。
今回のシンポジウムで感じたことは、それぞれのパネリストの立場の違いによる、語り口の違いであった。映画の中の大人びた生徒、シンポジウムで登壇した生徒、教育関係者の大人、学者の大人。それぞれ、特徴的な語り口がある。子供特有の抑揚というものは、誰もが思い浮かべることができると思うが、シンポジウムの壇上での生徒たちには、まだその名残がある。一般的な児童・生徒の「演技」である。大人たちはどうか。これは、おそらく、長い時間かけて、それぞれの立場、業種を生きぬ過程で、適応として得た「演技」の術ではないか。このような、長い時間をかけて得たものは、そのスパンの長さゆえに、あまり本人が自覚的に得たものではないように思う。それが、良いのか悪いのかは、わからないが、中には、長いものに巻かれたり、何かに目をつぶって過ごすうちに得てしまったものもあるように思う(とにかく、無意識に演技をしすぎ、させすぎ、させられすぎなような気がしている)。
その点、インタビュー・ドキュメンタリを通して得た「演技」とは、短い時間の中で濃縮された、インタビュアとインタビュイの間で交わされる思考の応酬の中で得られるもの。じっくりと自分が変わっている余地はない。常に、自分の心の変化、揺らぎ、動揺を、まざまざと見せつけられる。この過程が、「自分」というものへの自覚を要求する。
田口と福原、そして、担当教諭の先生によって仕掛けられたこの「暴力」は、明らかに、自我の萌芽を生んだ。編集の過程では、言葉の選び方、映像の選び方含め、全ての作業を、生徒一人一人が行う。
「言葉で言い表せないから、(ここは)映像なんだよね」
などと、田口に意見する。それでも言葉で表現してみることを田口は要求する。何を作品として残し、何を削るか、そこに、一人一人の意思が宿るし、それによって切り取られるインタビュイ達への責任も生じる。それでも、自分が感じたものは「これだ」と、カタチにしていく。この過程で、自分を見つける。もしくは、自分の演じ方を体得する。
映画上映の際、冒頭に監督である福原は「フィクションだから事実ではなく、ドキュメンタリだから事実だという、単純な二項対立ではありません」との旨、述べた。
そもそも、宗教観、政治観、異なる文化が混在し、いまだ科学的にも何が正しいかが判然としない事象が明らかとなっているこの社会において、何が現実で、何がフィクションなのか。
いずれにせよ、前回のレポートと同じ結論になるが、教育的場面において、年長者ができることというのは、学習者自らが演じるための舞台を用意することくらいなのではないか。そう、思った。
いつまでもただ席に着かせているだけでは、高校生は「高校生」のままだし、大学生は「大学生」のままだし、就活生は「就活生(その後の社会人)」のままである。
そのようなことを考えると、私自身に「舞台」を用意してくれた何名かの諸先輩がたを思い出す。ありがたいことである。
シンポジウム終了後、茶話会が宴もたけなわな頃に、生徒達から田口や福原に感謝の色紙が渡された。「あまり直接何かを教わったわけではないけど」と色紙を手渡される福原。前回のレポートでも「いつも冗談みたいなこと言ってる」と言われた田口。決して優等生とは言い難かった二人が(私も例に漏れないが…)、「先生!先生!!」と生徒に囲まれる姿が感慨深い。
最近、料理をするようになるようになって、ふと感じるのだが、やはり、自分が作る料理というのは、どこかで食べたものの真似事や、父や母がよく作ってくれていたものである。良きにつけ悪しきにつけ、好むと好まざるに関わらず、自分が関わった大人というものは、お手本にするつもりはなくても、どうしても影響を受けてしまう。私も大学人になるであろうし、その責任を改めて感じざるを得ない。自分は、どのような「大人」たり得るのか(注:ウチの両親の料理は美味しい)。
冗談のようなことを言う田口と、言葉少なにカメラを回す福原は、生徒達にとっては、道化と仙人のような存在であっただろうか。おおかみこども で言えば、韮崎のおじいちゃんと山の主の狐であろうか。そんな存在が、若い時には必要なように思う。
映画の途中途中で挿入される、学校の廊下や、風に吹かれるカーテンを見て、青葉山の麓にある、自分の高校のこと、高校生の頃の自分を思い出していた。
僕にも何人か、道化や仙人がいたのではあるが、それでも埋められなかった空虚感、おあつらえ向きな「演技」を要求される抑圧感を思い出す。
二人を道化と仙人に見立ててしまうのは、自分の心の穴を埋めたいだけかもしれないが、しかし、この先出会うであろう多くの後進に向けて、私ができるかもしれない数少ない演技の可能性を、そこに感じたことは、間違えない。
PS1
何かを自分で作りあげるということを体験しないと、必要なプロセスや技術というもの感じ取ることができない。そのような部分が、この社会の様々な機能を可能にしているのだが、そのプロセスや技術は瑣末な小事として、しばしばこの社会では無関心の対象となるのだろう。そしてその無関心は、想像力の欠如を生むのだろう。
PS2
ただし、「わけのわからなさ」というのにも2種類あるように思っていて、自分の想像力や知識・経験の欠如ゆえにわけがわからないだけの価値あるものと、ただ単に主張や論旨自体が間違っていたり意味をなしていないためにわけがわからないものがあるように思う。後者を後者であると判断するには、そうとうな状況証拠が必要なので、骨が折れる(前者は理解の枠組みを見つけられれば、自分が理解できるので、少なくとも自分にとっての価値は認められるようになる)。